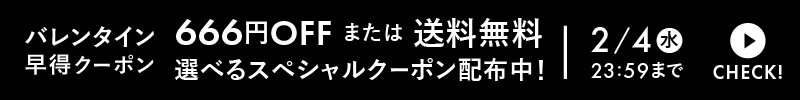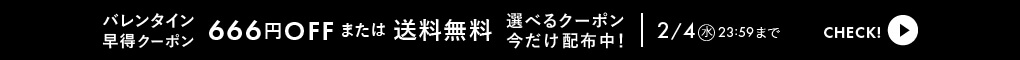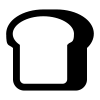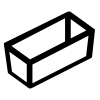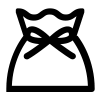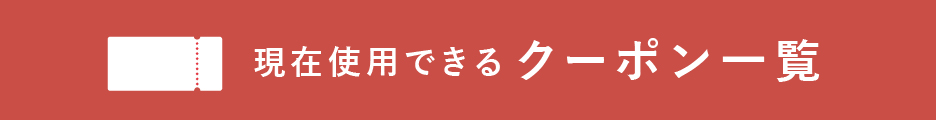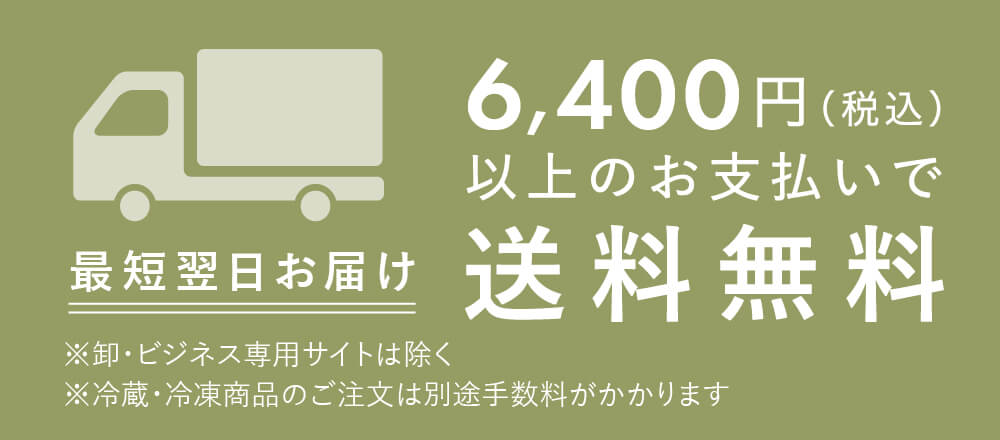Lesson 01
基本のこしあん
餡子(あんこ)とは
餡子とは小豆などの豆類を煮て砂糖を加え練り混ぜたものです。
豆は小豆の他に白いんげん豆(白あん)や青えんどう豆(うぐいすあん)、えだまめ(ずんだあん)等があります。
また、豆類以外ではかぼちゃや栗、さつまいもなどでんぷんを多く含んだ食材でも同様に作られます。
まんじゅう、ようかんなど様々な和菓子づくりのメイン食材になり、また「餡子×バター」など洋菓子やパンとの組み合わせも。
富澤商店では豊富な餡子のラインナップはもちろん、餡子を手作りしたいお客様にもたくさんの食材をご用意しています。

小豆から作る本格餡子
小豆からどうすれば美味しいこしあんができるのか?
今回はおさえておきたいポイントや動画をご紹介いたします。
手作りで作るこしあんはきっと、格別に美味しいものとなります。参考にしてみてくださいね!
期間限定
北海道産 特選小豆
10%OFF
- 期間
-
2024年3月1日(金) ~
2024年3月31日(日)
23:59まで
3ステップで学ぶ
作り方&ポイント


材料
-
通常価格383円 (税込)のところ
10%OFF 0,000円(税込)0,000円(税込)200g
-
0,000円(税込)
240g
-
0,000円(税込)
2.6g
-
水
適量
チェックボックスのない商品は只今在庫がありません。
はじめに、作り方を動画で
予習&ポイント
次に、3ステップで
流れをつかんで
01.煮る
-

01
鍋に小豆の量の1.5倍の水を入れて火にかけ、鍋の中央から泡が出るまで沸かす。 沸騰したら小豆を入れ、再沸騰してから水を一気に加えて差し水をして鍋から湯(差し水分)を取り除く。(6〜8回繰り返す)ざるに上げ、煮汁を切る。
POINT
水を加えて温度を60℃まで一気に下げること。
-

02
鍋に小豆の1.5倍の水を沸かし、重層と煮上がった小豆を入れる。再び沸いたら弱火にする。アルミ箔で鍋全体に蓋をし、柔らかくなるまで20〜30分煮る。
POINT
途中、水面から豆が出るようなら湯を足す。
02.こす
-

01
ボウルを2つ用意をする。1つめはざるをはめて煮上がった小豆を煮汁ごとレードルで1杯分すくってこす。もう1つは豆の皮が残ったざるを水をはったボウルに重ね、レードルでかき混ぜて呉(=生あん)を落とす。2つのボウルをひとつにまとめ、目の細かいこし器を使用してこす。
そのまま約5分おく。呉(=生あん)が沈殿したら、上水をそっと捨てる。(5〜6回繰り返す)POINT
水を多めに使うことによってさらす回数が少なく行える。
-

02
ボウルに沈んだ呉が見えるぐらい上水が澄んで来たら、さらし終わり。静かに上水をすてる。用意したガーゼを2枚重ねてボウルにかぶせて、さらした呉を一気に流し入れる。ガーゼの口を閉じて握るようにして水分を絞り出す。この時呉に水分が残らない様にしっかりと絞る。
03.練る
-

01
鍋に砂糖を入れ、呉の残りと、絞った呉の1/3量を加える。砂糖が溶けたら火を少し強め、混ぜながら110℃まで上げる。温度が上がったら弱火にして残りの呉の半量を加え練り混ぜる。ツヤが落ち着いてきてひとすくい持ち上げて形が残る程度が炊き終わりの目安。残りの呉を加え、均一に練り混ぜる。
POINT
水分を少し入れてあげる事によって砂糖を溶かす。
呉を3回に分ける事によってさらっとほぐれるような口どけの良いこしあんが作れる。 -

02
バットに移して粗熱をとる。粗熱が取れたら密着させるように、ラップをして完成。
プロに教わる!ポイント

渡邊 好樹(茶席用上菓子専門店『岬屋』店主)
「こしあん」を作るときのポイント
こしあんはとても上品な味わいに仕上がります。
その際なめらかな舌触りが重要になります。その舌触りを生む為には、工程の中で何回か行う濾すと言う作業とあんを炊き上げる際に鍋肌をしっかりと拭き取るのがポイントになります。
炊き上げの見極めとしては小豆と砂糖が完全に馴染んで来るとツヤが落ち着いて来ますのでしっかりとツヤが落ち着くまで炊き上げましょう。
これさえあれば始められる
基本の道具
-
このちょっと大きめサイズが、混ぜるのにも泡立てるにも使いやすい!錆びにくく、強度に優れているステンレス製。
0,000円(税込) -
目の細かいストレーナー(こし器)。
プリン液などをこしたり、小麦粉などの目の細かい物をふるったりするのに最適なストレーナーです。0,000円(税込) -
ほどよいしなり具合で扱いやすい!持ち手とヘラが一体となっているので衛生的、かつ適度な重さが使いやすいゴムベら。
0,000円(税込) -
あんこだけではなく炊きたてのカスタードクリームもバットにひろげて、氷水をあてればアッという間に冷ますことができます。効率よく作業できますよ。お菓子のみならず、お料理の下準備などにも活躍します。
0,000円(税込) -
お菓子作りを成功させるためには、1g単位ではかれるはかりが必須。すっきりデザインとお手頃価格で、はじめてさんにもオススメ。
0,000円(税込) -
お徳用サイズ。和菓子には必要不可欠な道具です。
0,000円(税込)